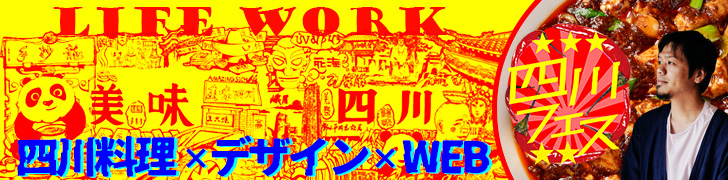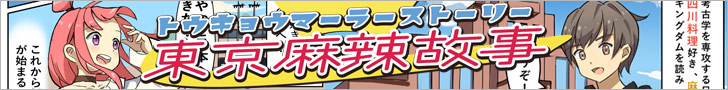雲南省大理の古鎮、諾鄧村へ
中国を旅してみたい、あるいは旅をしたことがある方、みなさんどのような場所を思い起こすでしょうか。その中にはひょっとしたら、雲南省と答える方もいるかもしれません。
では旅先に雲南省と答えた方々は、雲南のどのような場所を思い浮かべたでしょうか。その中にはひょっとしたら、大理と答える方もいるかもしれません。
雲南省大理はそれだけ中国国内外によく知られた魅惑の旅先であり、日本からもこれまで多くの観光客が訪れてきました。このたび私もそんな大理を旅しまして、いわゆる大理古城だけでなく、大理白族自治州の村や古鎮に遊びました。

そのうちの一つは、諾鄧村と呼ばれる古村落。大理古城から北西に160㎞、雲龍県中心部から3㎞ほどの山あいに位置する小さな村です。雲南民族文化をいろどる少数民族の一つ、白族(ペー族)が暮らす諾鄧は、唐代から清代に至るまで千年以上に亘りその地名を受け継いできたため、千年白族の村とも呼ばれています。

ところがいざ着いてみれば、村落は山腹へ張り付くように民居を集め、村内を移動する道といえばその隙間を縫うように入り組む急峻な石階段。車はもちろんバイクも通ることはできません。
────からん、からん、からん。
そこに鈴の音が通りました。その主は村人たちの大切な手足となる馬で、旅行者のスーツケースを一つ二つ三つ四つと背に負い不安定な石階段を下っていきます。と思えば、次は清掃員がまた、馬に巨大なゴミ袋を任せ村内を回っていきます。気がつけばここにもそこにも馬小屋があり、馬たちは大人しく草を食んでいました。
諾鄧とは虎のいる山腹という意味
この諾鄧という名は、白族の言葉で虎のいる山腹という意味をもつそうです。かつては急勾配ながら石階段で物を売るしかなく、そこに売り物の肉を狙ったヒョウが現れたものの階段を転げ落ち死んでしまった、そんな昔話を紹介する立て札もありました。
とにかくこのように移動もままならぬ急階段なのです。ぜえぜえと息を上げ休み休み登る私を涼し気な表情で見送る村人たち、彼らがたくましく思えてなりません。

迷路のように入り組んだ階段の道に迷っていると、土壁のお宅が並ぶ中でひときわ目立つ豪奢な門が見えてきました。塩課提挙司衙門です。
塩課提挙司とは明代に置かれた塩業を所管する官署で、全国に七か所、雲南に四か所配置されたうちの一か所がここ諾鄧にあったのです。村内には他、生産した塩を各地へ販売運搬する役目を担う塩局やその運搬道であった塩馬古道も残っていました。
諾鄧を千年白族の村たらしめたものこそ、この塩業の歴史でした。
史料を読み解き二千年もの歴史を数える一説もあるようですが、ここ諾鄧には少なくとも唐代には塩業が営まれていたといいます。諾鄧の歴史千年は、あるいはこの塩業の歴史千年と言い換えてもいいかもしれません。
塩を作っていた古井戸

村の足元には古井戸が残されていました。しかし井戸といっても、こちらは塩を生産するための塩井です。
四川では自貢の塩業が全国的に知られていますが、自貢の塩井は大木や竹を用いて巨大な滑車──天車を組み立て、その動力を利用して地下水を引き上げるものでした。一方でこちらの塩井にはそのような天車はなく、通常の井戸に用いられるような鶴瓶によって地下水を汲み上げていたようです。
ところがこちらの井戸、井戸穴が二つ並んでいるのです。この両者は地下で繋がっており、片方は淡水を、もう片方は塩を含む滷水を汲み上げるものなのだとか。このような井戸があるものなのですね。

古井戸のそばにはもくもくと湯気を上げる釜があり、塩が今にも生まれようとしていました。塩井から汲み上げられた地下水は、このように炊かれ塩になるのです。
科学技術の発展した現代に、このような古式製法はすでに不用のものとなりました。しかし村内には村が生んだこのような手作り塩が土産物としてそこかしこに売られており、なんと美味しそうに目に映ることでしょうか。
とはいえ目を惹きつけるのは塩だけではありません。石階段の脇に現れるお宅を覗けば、こちらのお宅にもそちらのお宅にも、巨大な琵琶型をした肉塊が大量に吊り下がっています。しかもそれはまるで、たわわに実る葡萄園のように隙間なく。
それは火腿でした。
雲南産の諾鄧火腿
火腿とはハムを指し、琵琶型をしたこれらの肉槐は豚の後ろ足、いわゆる生ハムになるものです。中国では浙江省金華市の金華ハム、雲南省豊靖市の宣威ハムなどがとりわけよく知られていますが、ここ雲南といえば雲腿とも呼ばれる宣威ハムが定番といえるでしょう。
しかし大理まで足を運べば途端に、宣威ハムよりも諾鄧ハムを一押しにしたレストランに出会うようになります。生ハムは肉を大量の塩で漬け込み脱水したのちに風乾熟成させるもので、塩業が盛んな諾鄧では古くから火腿生産もまた行われてきたのでした。唐代には南詔国(現在の大理)の国王がその美味に喜び、またその後の大理国時代には王室への献上品に、明代には東南アジア諸国へと流通したそうです。
そんな諾鄧ハムは今、千年のときを経て村人たちの手により継承されている。千年ものあいだ、人々を魅了し続けたその美味とはいったいどんなものでしょうか。

相変わらず村内の階段迷路を彷徨いながら、一軒のハム工房に出会いました。看板を見ますと、中国のドキュメンタリー番組「舌の上の中国」でも取材を受けたことのある工房だとのこと。現在のご主人は当家20代目となる方だそうで、ここまでくるともう老舗の域を超えた歴史の長さでしょう。

邸宅の中にある工房の扉を開けてくださいました。内部にはずっしりと重たそうな豚の後ろ足が眠り、ときを待っています。
商品として切り分けられたハムが真空パックされ棚に並んでいました。見ると二年ものと三年ものがあるようです。中国においてこのような生ハムは熟成三年を生食が推奨できる目安としているそうで、二年ものは蒸したり煮て出汁を取ったり、あるいは炒め物にしたりすることを推奨、三年ものには生食可能なハムとして付加価値が付けられていました。

私が選んだのは三年もの。ずっしりと手に重さ感じる立派な諾鄧ハムはまるでザクロの果実のように鮮やかで輝くような色合いをしており、もう見るからに美味しそうです。およそ750ℊで180元(約3600円)という価格でしたが、三年の眠りを経たことを考えれば決して高い買い物ではないでしょう。
諾鄧ハムを食べる

彷徨いながら目指していた宿はこのハム工房の先、諾鄧村の家々を上から見下ろす高さにありました。
家庭的な民宿であり、頼めば料理も作ってくれるといいます。せっかく購入したばかりとはいうものの、まだ封を開けることはできません。けれども帰宅まではとても我慢できそうもなく、それならばぜひ、ハムを生み出すご本人たちの手で調理されたものを味わってみたいものです。
「ハムが食べたいんですが……」
「もちろん!それなら、うちのハムを見てみる?」

勧められるがまま奥までついていくと、扉の先には圧倒されるようなハムの森が隠れていました。左の部屋が二年もの、右の部屋が三年もの、合わせて三桁には及びそうな数です。
このように立派なハムを目の前にしてわたくし事を語り恐れ入りますが、実は二年前の冬に私も生ハム作りに挑戦したことがありました。あの時は塩漬けと脱水におよそ一か月を掛け、燻製と合わせ風乾に二カ月、ところが仕上がったものはまあまあ食べられるものの予想以上に形が縮み、大成功とはいえないものでした。
思い返してみれば、小さな肉塊を生ハムにするだけで驚くほどの塩を使いました。ならば、これほどまでに大量のハムを仕上げるのにいったいどれほど塩を使うのでしょうか。それになによりあの苦労を思い返してみますと、これだけのハムをご一家で作り上げるのは相当な労力であるに違いありません。

その貴重な、宿ご自慢のハムをいただきます。一品は、ジャガイモや唐辛子やハムを炒めたもの。もう一品は、生食のためにスライスしてくださいました。
ハムを野菜で炒めたものは何度も味わったことがありますが、ジャガイモ炒めは初めてでした。雲南はジャガイモの産地でもあり、ただでさえ美味しい。それにハムの塩味と旨味が移り、なんと美味しい。けれども醍醐味といえば、やはりスライスの生食でしょう。透き通るほどまで薄くそぎ落とされたそれは欧州産のものに勝るとも劣らず、「食べきれなければ持ち帰ります」などと申し伝えておきながら、トウモロコシを原料にした村自慢の白酒も進みぺろりと平らげてしまいました。
茶館で塩茶を飲む

────翌日。
今日は大理古城へ戻らねばなりませんが、不規則に重なる瓦屋根やどこかしらから耳に届く馬の鈴音、雄大に広がる山肌の見晴らしに後ろ髪が引かれます。
「バイバイ!」
よちよち歩きのお孫さんとともに見送ってくれた宿のおじいさん。そんな温かさも私を引き留めます。結果、石階段を下りようとしながらも帰りを引き延ばす言い訳にしたのは、一軒の茶屋でした。

茶屋にはお茶をはじめジュースや自家製の果実酒などが用意してありましたが、その中で目に留まったのは塩茶というものでした。
「どんなもの?」と尋ねますと、ここ諾鄧村の近くにあります宝豊鎮の緑茶に雲南で採れる苦子果という実を合わせたお茶、それに塩を使うというのです。やってもらいますと、茶葉で淹れた急須に、なんと岩塩をそのまま投じました。
「長く浸けてはダメ、少しでいいの」
そう話しながら、さっと岩塩を拾い上げます。さっそく急須を傾けましてそのお茶を味わってみたところ、ほんのりかすかに塩味が香り、そこに茶葉の旨味と苦子果の苦味が引き立ちなかなか美味しい。塩分といえば血圧を上げそうなものですが、この塩茶にはほてりを鎮める効果があるのだそうです。
しかしいつまでもこうしているわけにはいきません。心の中で村にサヨナラを告げながら、今度こそと石階段を下っていきました。
すると、さきほどバイバイしたはずの宿のおじいさんが向こうから────。
「あんた、まだいたの?」
「そろそろね。でも最後に塩水魚を食べて帰ろうと思って」
諾鄧村には塩水魚と呼ばれるものがあるそうで、珍しさもあり昨晩お願いしてみたばかりでした。しかし塩水魚といっても、それは大海で採れる海魚のことではありません。塩業を生業にしてきたこの村にはなんと塩水を用いて鯉を養殖する技術があるのだそうで、それをここでは塩水魚と呼ぶのです。
ところがそれは、それがある店に行かなければない……と。そうして諦めた昨晩だったのでした。
「ダメだ、ダメだ。あんたじゃ見つけられないぞ」
ひょんなことから、今日一日またおじいさんにお世話になることとなりました。

おじいさんが案内してくれたのは、諾鄧村の出口から1㎞ほど山を下ったところにある塩水魚の養殖池でした。一見してはなかなか飲食店とはわからないものの、奥へ進めば火鍋テーブルが用意されており店の人が迎え入れてくれました。
この養殖池を満たすのは、村の塩井から引かれた塩を含む地下水。淡水魚である鯉はもちろん本来は塩水で生きることはできませんが、塩水と淡水を合わせた水で一度慣らした後ここに鯉を放つのだそうで、言葉では易くともやはり技術がなければうまくいかないでしょう。村の個人宅にこの塩水魚がないのも納得、必要な時にはここから魚を買うのだそうです。
鯉の魚火鍋を食べる

では、この塩水魚を使いどのような料理がいただけるのでしょうか。お願いしてみますと、「一人なら一番小さな鯉を探しましょう」と店の人は養殖池にタモ網を沈めました。それを引き上げれば、活きのよい鯉が網の中で暴れています。選ばれたのは、一番小さな……といってもやはり立派な鯉一尾。厨房へと運ばれていきました。

ほどなくして用意が出来上がったのは塩水魚の火鍋でした。諾鄧村の塩水で育った鯉と、同じく諾鄧村で生まれたハム。この両者が手を繋いだ火鍋です。
たっぷりと肉をつけた鯉のぶつ切りと桜色をしたハムのスライスが、ぐつぐつと沸き立つスープの中に見え隠れしています。それをお玉ですくい、発酵豆腐調味料である腐乳にネギやニンニクを添えたタレに。かぶりついてみれば、それは鯉でありながら鯉とも異なるような、新しい味覚との出会いでした。

貴重なハムを惜しげなく使ったスープにはその出汁がよく効いていました。そのスープを吸った白身はふわりとした食感ながら旨味が立ち、やはり鯉ではありますから骨には注意が必要ですが、風味には海魚のような食べやすさがあります。
千年白族の村で受け継がれてきた塩業、その源である塩水で育つこととなった鯉、そしてそんな塩がなければ生まれ得なかったハム。山あいに隠れた小さな村にはこんな美味しさと村人たちの誇りが息づいていました。
基本情報
諾鄧魚庄
雲南省大理白族自治州雲龍県諾鄧村諾鄧公路204号(村出口から雲龍県市街方面へ1㎞)
営業時間 8時~21時
火腿魚火鍋 鍋一式:25元、塩水魚:30元/500ℊ
四川の名物料理の関連記事
- 宜賓の路地裏グルメ「点点香」!麻辣燙でも冒菜でもない四川の隠れ名物を食べる 2025年11月30日
- 【無形文化財】宜賓横江古鎮のご当地スイーツ「眉毛酥」の物語と古い街の散策 2023年06月22日
- 【四川地方料理】平楽古鎮で食べる邛崃名物!白濁した濃厚スープの奶湯麺と甘辛の鉢鉢鶏は絶品 2023年02月19日
- 売上高1.2兆円!宜賓を支える老舗酒造「五糧液」を見学し、名物の南瓜田鶏(かぼちゃとカエル)をつまみに白酒を飲む旅 2022年12月16日
- 古建築が残る李庄古鎮で李庄三白(白酒、白糕、白肉)を味わい、歴史を考える。 2022年07月11日
- 成都女子、四川で一番大きな烤魚「至尊巨無覇烤魚」を食べる! 2022年03月28日
- 中国市場を独占!レモンの都、四川省安岳県で食べる名物料理「魚蛋」と穴場の石刻巡り 2021年08月20日
- 学生たちと人気串串火鍋「牛華八婆」で打ち上げ!ほのぼの宜賓生活に癒される1日。 2021年06月14日
- 鶏の黄金スープに豚つくね!伝説の「高県土火鍋」をついに食べました!! 2021年04月06日
- 三国志ファン必食「剣門豆腐」!難攻不落の要塞「剣門関」で食べる四川名物料理 2021年02月15日
麻辣連盟 | 四川料理を愛する仲間たち

四川料理を愛し中華料理が大好き!麻辣連盟では普段日本で食べられている四川料理ではなく、本場の料理を皆で食べる食事会を中華料理店とコラボして、全国で開催します。食の好奇心に刺激され、まだ見ぬ大陸の味を日本で食しましょう!参加される方は入党ください!
【出版】四川省・成都を中心にした食べ歩き旅行の決定版
書肆侃侃房 (2014-08-25)
売り上げランキング: 30,730
SNSでも発信しています!
おいしい四川公式ページ
最新四川料理はXにて!
【四川料理の旅】取材記録を公開中!
ご案内
人気記事まとめ
- 日本炒飯協会がオススメ!横浜で食べてほしいチャーハンベスト5
- 麻辣宣言!四川フェスNo1売上の陳家私菜と商品開発!イトーヨカドーが仕掛けるお惣菜革命
- 日本で食べる最高峰レベルの烤魚!伊勢佐木町にある小青椒
- 【成都】これが最高傑作!これ以上の夫婦肺片はない「黄傘肺片」
- 大きすぎる!自家製豚で作る伝説の料理「連山回鍋肉」
おいしい四川運営者について
辛い料理と食べ歩きを愛している方に、日本にはない本場の料理を食べるチャンスを提供する「四川料理の専門家・麻辣連盟総裁」の中川正道です
お気軽に友達申請ください。申請時は一言お願いします! facebookを見る
世界を遊び場に生きる

中川正道、1978年島根県生まれ。四川師範大学にて留学。四年間四川省に滞在し、四川料理の魅力にはまる。2012年にドイツへ移住。0からWEBデザインを勉強し、フリーのデザイナーとしてドイツで起業。2017年に日本へ帰国。「人生の時を色どる体験をつくる」をテーマに妻の中川チカと時色 TOKiiRO 株式会社を設立。
四川料理マニアたちがつくる四川料理の祭典「四川フェス」主催。過去動員数累計24.5万人。四川料理、しびれ、麻辣、マー活ブームに火をつけ中華業界を盛り上げる。